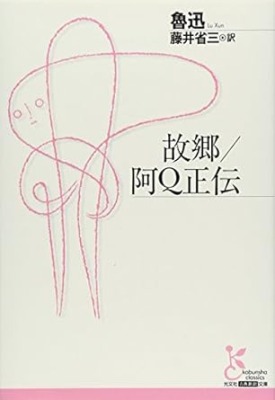中国の文学者である魯迅がもし生きていたら、今の中国をどう観て、どう語るだろうか。中国共産党は魯迅を「革命の聖人」と祭り上げてきたが、魯迅がそれを喜んで受け入れるとはとても思えない。権力や「正しい人」や奴隷的精神に魯迅ほど鋭い刃を向けた文学者はなかなかいないからだ。
魯迅が晩年を過ごした上海において厚い親交があった内山完造が、肺を病んで死期に近いようにみえる魯迅に、日本に転地療養して静養することをすすめた時、魯迅は「日本語の静養とはどんな意味か」と尋ね、内山が「何も考えず、ぼんやり何もしない、ふらふら遊んでいることですよ」と答えたら、次のように答えたという。
「いけないねぇ。それはできない。今、われわれの前には砂漠が迫りつつある。どうしてぼんやりと遊んでなどいられよう。」
中学生の時に最初に読んだ時はわけのわからない妙な読後感しか残らなかった「狂人日記」や「阿Q正伝」は、辛亥革命や袁世凱独裁で揺れる当時の中国にあって、魯迅は何を希求したのかをいくらかでも知れば、破格の毒を含んだ文学―日本には極めてまれな性格の―であることがみえてくる。
希望がないことに確信があったとしても、「絶対ないとはいえない」以上、戦い続ける―この姿勢は、「狂人日記」執筆のきっかけとなり、魯迅の転換点ともなった、「鉄の部屋」のエピソードとして知られる、友人の銭玄同との対話から触発されたものだが、魯迅はそれをその後の生涯で貫いたように思える。